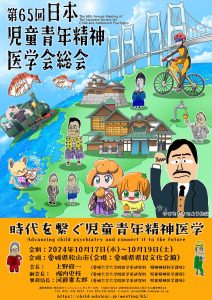Course introduction
講座紹介
提案型寄附講座
児童精神医学

愛媛県の子どもたちのこころを育み、
愛媛県で子どものこころ専門医を育てる
児童精神医学講座は、愛媛県との協働のもと、愛媛県における子どもの精神科医療を発展させることを目的として設立された講座です。
全国的な子どもの数の減少と相反して、精神的な不調をかかえる子どもは増加しています。子どもたちは心に不調を感じても、なかなか誰かに相談できません。子どもの心の不調は「家庭や学校の問題」と捉えられがちでした。しかし、少しずつ身体のみならず心の不調についても病院で相談ができるものと理解されるようになり、児童思春期外来を受診する子どもたちが増えてきました。一方で、児童思春期を専門とする医師は、全国で650名ほど不足しています。愛媛県の「子どものこころ専門医」は現在7名ですが、到底十分とはいえません。何とかこの状況を打破したいと考えています。
子どものこころを育むということは、医療だけでなく、教育・福祉・行政・医療が一体となって取り組むべき課題です。この児童精神医学講座が、より良い連携・協働のためのファシリテーターを担っていきます。
【講座問い合わせ先】
提案型寄附講座 児童精神医学講座
〒791-0295 愛媛県東温市志津川454
TEL:089-960-5315 / FAX:089-960-5317
【関連HP】
精神神経科学講座 https://www.m.ehime-u.ac.jp/school/neuropsychiatry/
愛媛県発達障がい専門医療機関ネットワーク構築事業 https://www.m.ehime-u.ac.jp/neurodevelopment/
愛媛大学医学部附属病院 子どものこころセンター https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/department/子どものこころセンター/
 サイトマップ >
サイトマップ >  お問い合わせ >
お問い合わせ >  English >
English >