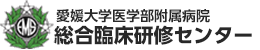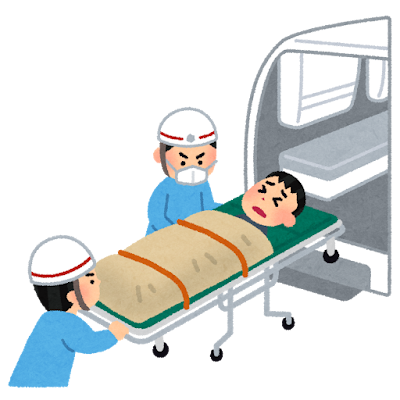研修医の一次・二次救急研修報告「めまい診療の奥深さ」
アイプログラム(愛媛大学医学部附属病院を中心とした研修プログラム)では、救急研修の一環として、大学病院に隣接する愛媛医療センターで研修医が一次・二次救急の診療にも当たっております。熊木天児センター長が指導医として同行することもあり、センター長から与えられたお題に応えるように、研修医の皆さんに経験談をレポートして頂きました。どの研修医も学びに繋がるしっかりとした研修を受けております。
第1弾でご紹介するのは、めまいの症例から多くのことを学べたという2名の研修医の経験です。3日連続で投稿していきますので、ぜひご確認ください。
A先生(1年目研修医):めまい診療の奥深さを経験
めまいのため、ご家族に付き添われて来院された80歳以上の男性を担当しました。3時間前からの浮動性めまいと気分不良を訴える方でした。鑑別として、熱中症や良性発作性頭位目眩症(BPPV)も考えられました。しかし、ご本人は意識あるものの応答が乏しく聞き取りが難しく、回転性の判断が難しかったです。そこで、まず除外しなくてはならない疾患として頭部病変があげられたため、単純CT検査を受けていただきました。その結果、小脳出血と診断されたため大病院への紹介となりました。
センター長からはまず除外したい疾患として頭部病変と心病変があり、疑わしい場合では検査を怠ってはならないとご指導いただきました。今回の症例は、めまいというよくある症状から脳出血という重篤な疾患が判明したものであり、これを教訓に疾患の初期症状を見逃さず対応することを心がけていきたいと思います。
B先生(2年目研修医):嘔吐後にも関わらず嘔気の続く場合には無痛性心筋梗塞の除外も
今回、救急外来で「嘔吐」「浮動性めまい」「気分不良」を主訴に救急車搬送された方を1年目研修医とともに担当しました。夕方頃から畑仕事をしていて気分不良(めまいも併発)を感じ、数回嘔吐があった、真夏だった、というエピソードから熱中症を考えました。しかし、体温上昇や皮膚ツルゴール低下はなく、腹部所見も目立ったものはありませんでした。進行した肺がんの加療中でしたが、ADLは自立されている方でした。そこで、頭部病変、急性冠症候群、消化管通過障害などを鑑別に挙げ、各種採血、CT検査、心電図を確認しました。
センター長から持続する嘔吐や嘔気がある場合には無痛性心筋梗塞を除外する必要がある、とのアドバイスから心電図、心筋トロポニン等も確認し、対応しました。結果的には、頭部CTで小脳に出血があり、高次医療機関に紹介、救急搬送となりました。
嘔気、嘔吐といった症状から無痛性心筋梗塞の可能性もあるというアドバイスはとても勉強になりました。現在、地域医療で研修している病院の救急外来でも、同じ症状で搬送されてきた無痛性心筋梗塞だった症例があり、心筋梗塞を鑑別に挙げて対応できました。様々な経験をして知識の蓄積をしていくことが改めて大事だと確認することができました。
センター長からのコメント
めまい〜失神〜意識障害を訴える場合、慎重に鑑別診断を進めなければなりません。とは言いますが、時として難しいことがあります。私自身はめまいの患者さんを診た場合、明らかに失神ではなさそうであっても、常に失神の鑑別として重要な心原性および脳血管性を一度は想起するように心掛けております。なぜなら、目撃者のいない場合もあるからです。特に、「あれっ?何か典型的な症状ではないな」と思った時こそです。今回の場合、熱中症も鑑別にあがりましたが、「何か違う!」と感じました。言語化できれば良いのですが、その時こそ「あれっ?」なのでしょうね。無痛性心筋梗塞のリスク因子として高齢、女性、糖尿病があげられており、消化器症状(嘔吐、下痢)として発症する下壁梗塞を知っておくことは重要です。
B先生、救急車への同乗お疲れ様でした。私とLINEで繋がっているとは言え、緊張したことと思います。もう25年前のことになりますが、ドキドキしながら搬送したことを思い出しました。その後、搬送先から連絡があり、小脳出血は脳転移に伴ったものかもしれないというものでした。
2人とも1人の患者さんから多くのことを学びましたね。医学生や研修医は、ついつい数を求めがちですが、質の方がよほど重要です。質を高めてから数をこなせる医師として成長してください。
愛媛大学の臨床研修「アイプログラム」では、診療の質にこだわり、研修医の着実な成長に注視しております。