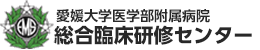ハワイ大学医学部(JABSOM)臨床実習生とのシミュレーター実習交流を開催しました(2025年3月28日)
愛媛大学医学部では、2025年3月24日(月)から28日(金)までにハワイ大学医学部(John A. Burns School of Medicine: JABSOM)からの臨床実習生2名を迎え、28日には本学の学生との「シミュレーター実習交流」を開催しました。今回が初めての試みとなるこのプログラムは、過去に本学の学生がJABSOMにおいて体験したシミュレーター教育に着想を得て企画され、国際的な視点からの医学教育の実践と、相互理解の促進を目的としています。
当日は、ハワイ大学医学部の最終学年である4年生2名(男性1名・女性1名)に加え、愛媛大学医学部医学科の1年生から5年生までの学生7名、および歯科の研修医3名が参加し、職種・学年を超えた「チーム医療」の体験の場となりました。実習は英語を用いて行われ、BLS(Basic Life Support)および気管挿管の2つの内容について、愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター長の熊木天児先生の指導のもとで実施されました。
BLSのセッションでは、患者の発見から胸骨圧迫(chest compression)、バックバルブマスクによる人工呼吸といった一連の流れを、参加者がチームで協力しながら行いました。特に、使用したシミュレーターでは、胸骨圧迫の深さやリズム、換気量などがリアルタイムで見える化され、実技の質を客観的に評価することができました。チーム内でスコアを比較し合いながら、お互いにフィードバックを行う場面も多く見られました。また、英語での実習らしく、AEDを作動させる場面では「危ないから離れてください」ではなく、“Clear!”という指示が出ておりました。
気管挿管のセッションでは、医師役・助手役を交代しながらローテーション形式で練習を行い、正確な手順の確認や役割分担の重要性について理解を深めました。実際の臨床現場を想定した手技トレーニングは、学生たちにとって貴重な経験となりました。
参加した学生からは、「緊急の場面では、その場で初めて顔を合わせたメンバーと連携を取ってBLSを行うことがある。その際、英語でのコミュニケーションという状況下で、自分の意思をどのように伝えるかを考える良い機会になった」、「言葉だけでなく、身振り手振りやアイコンタクトなどの非言語的な手段も重要であると感じた」、「それぞれが得意・不得意を補い合いながら、即席のチームでもしっかりと役割分担し、協力してBLSを遂行する大切さを学んだ」といった声が聞かれました。
今回の実習は、国籍や言語の違いを超えて協働する力、そしてチーム医療の実践的な意義を実感する貴重な機会となりました。今後もこうした国際的な交流を通じて、より多くの学びの場を提供できるよう努めてまいります。ご協力いただいた全ての皆様に心より感謝申し上げます。