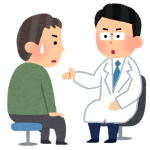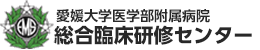研修医の一次・二次救急研修報告「大動脈解離、急性心筋梗塞を疑う症例」
アイプログラム(愛媛大学医学部附属病院を中心とした研修プログラム)では、救急研修の一環として、大学病院に隣接する愛媛医療センターで研修医が一次・二次救急の診療にも当たっております。熊木天児センター長が指導医として同行することもあり、センター長から与えられたお題に応えるように、研修医の皆さんに経験談をレポートして頂きました。どの研修医も学びに繋がるしっかりとした研修を受けております。
第3弾でご紹介するのは、普段から救急外来の現場での動き方をイメージしながら勉強することの大切さを学べたという経験です。4日連続で投稿していきますので、ぜひご確認ください。
「大動脈解離、急性心筋梗塞を疑う症例」(2年目研修医 C先生)
先日の救急外来で胸痛を主訴にウォークインで救急外来を受診された方を担当しました。当日の夕方頃に突然発症の胸痛を訴え、前医を受診されました。診察の結果帰宅されたものの、胸痛が治らず再度救急外来を受診されました。来院時は落ち着いていましたが血圧200台の上昇、移動する背部痛、握力の低下などを認めており、急性心筋梗塞、大動脈解離などを鑑別に上げました。高血圧緊急症として降圧を考えましたが、上級医の先生から、脳梗塞の可能性があるため慎重な降圧を行うようご指導いただきました。慢性腎不全があり造影CTを撮ることができず、心電図、単純CT、MRIを行いましたが、心電図変化、解離や脳梗塞の所見はなく、降圧をおこなって経過観察を行なっているうちに痛みは軽減し、後日通院中の総合病院を受診していただく方針となりました。
今回の症例を経験して、胸痛を見たらまずは4killer chest painを除外すること、普段から救急外来の現場での動き方をイメージしながら勉強することが大切だと感じました。愛媛医療センターの救急研修ではすぐに指導医に相談できる環境が整っており、安心して診察することができますが、自分1人で対応しないといけなくなる3年目以降に向けてしっかり経験を積んでいきたいです。
センター長からのコメント
医療センターの常勤医とともに、私も診療に関わりましたが、本人および家族からの情報が少なく、内容も二転三転する感じもあり、方針を決めるのに難渋した患者さんでしたね。しかし、そんな状況の中、こまめに足を運び経過を観察でき、ゆっくりながら降圧も図ることができたと思います。痛みを有する患者さんを診た場合、これからも本命・対抗馬を考えるとともに、致死的な大穴を考え得る癖をつけて下さい。