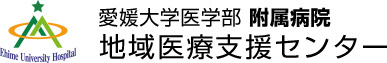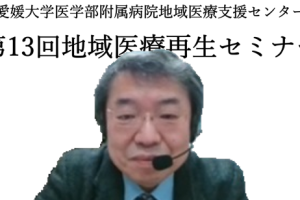第13回地域医療再生セミナーを開催しました【令和6年10月31日(木)】
令和6年10月31日(木)、愛媛大学医学部附属病院地域医療支援センターでは第13回地域医療再生セミナーをオンライン開催し、学内教職員のほか、愛媛県及び県内各市町の行政機関、各関連病院等から約50人の参加がありました。
地域医療支援センターでは、地域医療に従事する医師を確保し、その定着を図ることにより,医師の地域偏在を解消するための事業を実施しています。その一環として,県内各地域の医療体制の現状と展望、地域医療における機能分担や医療連携等について、関係者の理解を深めることを目的とした「地域医療再生セミナー」を毎年開催しています。今回のセミナーでは、地域医療関係各講座等の取組を紹介したほか、演者をパネリストとして「地域医療の充実・発展を目指して」と題した討論会を行いました。
始めに、杉山隆病院長から開会挨拶の後、高田清式地域医療支援センター長が「地域医療支援センター活動報告」と題し、講演を行いました。
- 杉山 隆 病院長
- 高田 清式 地域医療支援センター長
- 羽藤 直人 医学系研究科長
続いて、7寄附講座から8名の教授による取組紹介の講演が行われました。演題は以下の通りです。
・「地域医療学講座の活動報告」 川本龍一 地域医療学講座教授
・「地域医療再生学講座 令和6年度活動報告」 間島直彦 地域医療再生学講座教授
・「愛媛大学地域救急医療学講座の歩みとこれから」 井上勝次 地域救急医療学講座教授
・「地域小児・周産期学講座 10年目の歩み ~子どもたちといっしょに私たちにできること~」
檜垣高史 地域小児・周産期学講座教授
・「シミュレーション教育で守る愛媛の周産期医療」 松原圭一 地域小児・周産期学講座教授
・「救急航空医療学講座活動報告」 竹葉淳 救急航空医療学講座教授
・「地域生活習慣病・内分泌学講座15年間の総括」 松浦文三 地域生活習慣病・内分泌学講座教授
・「地域低侵襲消化器医療学講座 令和6年度までの活動報告」 石丸啓 地域低侵襲消化器医療学講座教授
-
地域医療学講座
川本教授
-
地域医療再生学講座
間島教授
-
地域救急医療学講座
井上教授
-
地域小児・周産期学講座
檜垣教授
-
地域小児・周産期学講座
松原教授
-
救急航空医療学講座
竹葉教授
-
地域生活習慣病・
内分泌学講座
松浦教授
-
地域低侵襲消化器
医療学講座
石丸教授
その後、羽藤直人医学系研究科長及び高田清式地域医療支援センター長を座長として、「地域医療の充実・発展を目指して」と題した討論会を行いました。
高田センター長から「各寄附講座を今後も維持し発展させるために、どのような課題がありどのような取り組みが必要か」という地域医療の現状と将来についての問いかけに対し、パネリストからは下記のような意見がありました。
*「開業医が減っており、寄附講座の役割も大きくなってきている」
*「ドクターヘリに一緒に乗って学んでくれる若手医師を育成する必要がある。そのため、ドクターヘリ見学会は
高校生や看護学生も参加できるように間口を広げている」
*「地域住民の健康を守るための市民講座を最低でも年に1回は実施しており、今後も継続していく」
*「まずは地域の住民に認めてもらえるような様々な取り組みを行う。その上で市町と連携し、病院の機能統合と
いう前向きな言葉で医療体制の再構築を考えていく」
*「救急の医師は不足しており、また専門外の患者も多い。各講座の横の連携を強化し発展させていく必要があ
る」
これらの意見を受け、羽藤直人医学系研究科長より「地域枠の導入で医師の数は増えているが、偏在化は解決しておらず、地方の医師不足は大きな課題。現在20名いる地域枠のうち恒久定員は5名で、現状が約束されているのは令和8年度まで。10年先を見越して今後の愛媛の医療体制を考えていかねばならない」と閉会の挨拶をいただきました。
本セミナーを通して、参加者全員が地域医療の現状と将来について共に考え、諸課題の解決に向けて連携して対応するための良い機会を持つことができました。
本センターでは、これからも地域医療再生セミナー等を通じて情報を発信し、関係機関とのネットワークを強化し、地域医療を担う医師の養成を推進してまいります。
掲載日:2024年11月18日