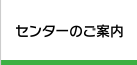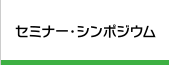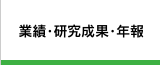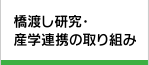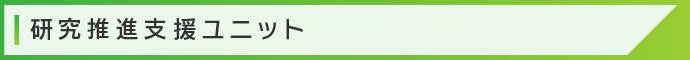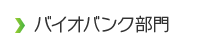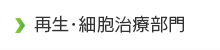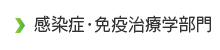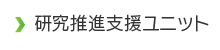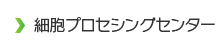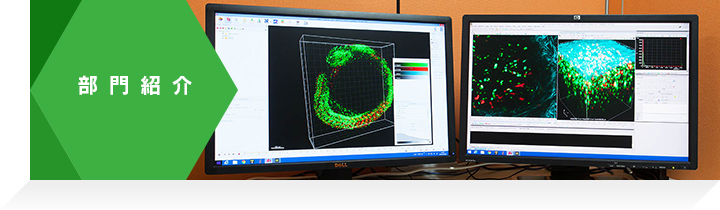
スタッフ一覧
- 三宅吉博(ユニット長)
- 齋藤 卓(副ユニット長)
「根拠に基づく医療(Evidence-based Medicine: EBM)」の根拠とは、疫学研究で得られた研究成果のことです。本来、生活習慣、生活環境、遺伝的背景の違いから、欧米人を対象とした疫学研究で得られたエビデンスを日本人に直ちに適用すべきではありません。本邦では、疫学研究に基づくエビデンスが極めて少なく、疫学研究を適切に推進し、エビデンスを創出できる人材の育成が喫緊の課題です。
疫学研究の第一義は、一次予防(疾病発症予防)に資する公衆衛生の疫学研究です。3歳児や小中学生を対象とした横断研究、潰瘍性大腸炎等難病の症例対照研究、妊娠中から生まれた子を追跡する出生前コーホート研究、成人を対象としたコーホート研究といった観察的な疫学研究を基軸として研究を推進しています。
平成27年より成人を対象とした「愛大コーホート研究」を開始しました。順次、愛媛県内19市町でリクルートを行い、8年かけて10359名が参加しました。令和2年度から5年目追跡調査、令和7年度から10年目追跡調査を行っています。一方、約1万人のコーホート研究では発症頻度の低い疾患では発症者数が少ないため、リスク要因の解析ができません。そこで、心房細動、乳癌、関節リウマチ患者を令和7年度よりリクルートし、コーホート内症例対照研究を実施します。
また令和6年度より次世代医療基盤法に基づき、愛媛全県民の保健医療福祉情報を名寄せ突合する愛媛リアルワールドデータ構想を推進しております。愛大コーホート研究のデータも愛媛リアルワールドデータに突合することで、脱落のない完璧な追跡、様々なアウトカムの把握が可能となります。様々な疾患発症のリスク要因や予防要因を解明するだけでなく、特定の疾患の予後に影響する要因の解明、さらには、市町や県の保健医療福祉行政に資する解析も行います。
臨床研究の大部分は臨床における疫学研究です。一次予防に資する疫学研究を学べば、臨床での観察的疫学研究や介入研究(医師主導治験)への応用展開が容易となります。これから臨床研究を極めたい若手医師は医農融合公衆衛生学環で公衆衛生学修士、医学専攻で医学博士を取得する道を強くお勧めします。
今後も引き続き、愛媛大学において臨床における疫学研究が革新的に発展するために努力して参ります。国際的治験等受託研究を多数獲得して、愛媛大学病院は臨床研究中核病院を目指しましょう。
1.愛大コーホート研究
成人を対象とした20年間追跡する前向きコーホート研究です。
2.九州・沖縄母子保健研究
平成19年より妊婦さん1757名を追跡している出生前コーホート研究です。
3.日本潰瘍性大腸炎研究
症例群として52医療機関から計384名が研究に参加しました。対照群は愛媛大学及び関連病院から666名が研究に参加しました。
生体内部の構造や機能を画像として可視化する技術であるバイオイメージングは近年大きく進歩しており医療や基礎医学研究において欠かせないものとなっています。このイメージング技術の発展に伴い、デジタル画像データからコンピュータによる解析を通じて生体情報を定量的に評価する技術も発展しています。このような研究は今後のイメージングに基づく精密な計測さらに正確な診断に欠かすことのできない技術になります。
イメージングインフォマティクス支援では、画像情報の自動定量化法の開発と支援を行っています。バイオイメージング部門と連携し、先端的イメージング法と連動した新規解析法の開発も行っています。
1.非線形光学顕微鏡を利用したデジタル病態診断法の開発研究
病理組織形態の数値化から自動診断支援までを行うデジタル病理学は,より客観的でより迅速な画像診断を可能にすると期待されています.非線形光学顕微鏡を利用した染色や特殊な加工を必要としない分子イメージング技術と画像インフォマティクスを融合させることで新規の病態評価システムの開発研究を行っています。
2.多次元データ解析技術の開発研究
医療画像、また、顕微鏡画像の1つの大きな特徴は多次元的に生体内部を画像化していることです。多次元的とは、立体(3次元)画像に加えて時間やスペクトル情報を合わせたものです。我々はこのような生体画像特有の画像解析方法の開発を進めています。多次元的な組織形態情報から新たな病態把握・診断技術の提案に繋げる研究を行っています。