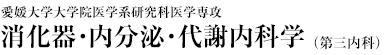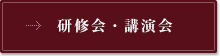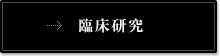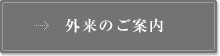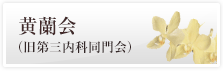第12回肝不全治療研究会が開催されました
2010年9月11日 11:32 PM
9月10日(金)に富山国際会議場で第12回肝不全治療研究会が行われました。今回の当番世話人は愛媛県立中央病院の道堯浩二郎先生でした。第17回門脈圧亢進症学会の附置研究会として開催されました。学会第2日目の午前中に行われました。
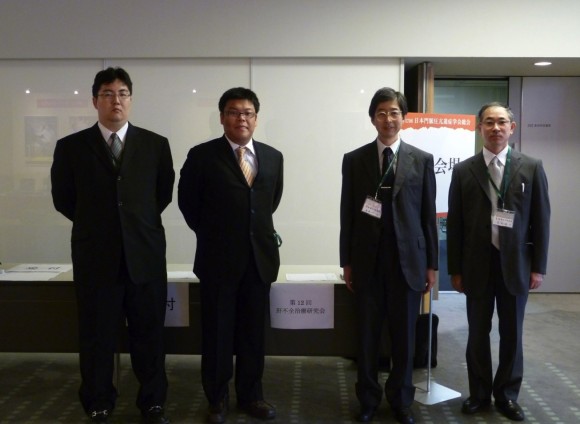
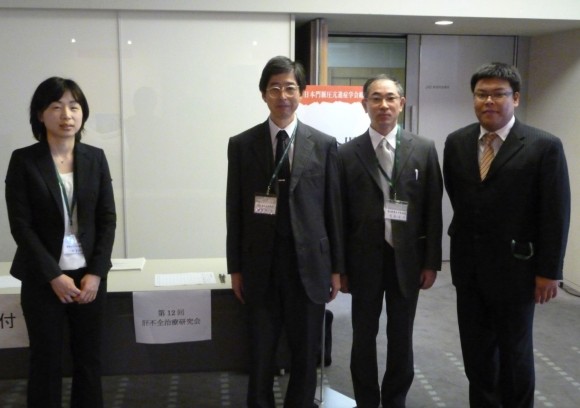 研究会開始前にスタッフで。当番世話人の道堯先生、事務局で尽力された宮本先生(当日は会場運営、カメラ係)、受付で中原先生と木阪先生、アナウンス担当で一柳先生が奔走していました。
研究会開始前にスタッフで。当番世話人の道堯先生、事務局で尽力された宮本先生(当日は会場運営、カメラ係)、受付で中原先生と木阪先生、アナウンス担当で一柳先生が奔走していました。
 当日の受付風景。迫力ありました。入り口での威圧感にもかかわらず多くの人に参加していただき盛況でした。
当日の受付風景。迫力ありました。入り口での威圧感にもかかわらず多くの人に参加していただき盛況でした。
 代表世話人の森安先生に続いて、当番世話人の道堯先生よりあいさつが行われました。
代表世話人の森安先生に続いて、当番世話人の道堯先生よりあいさつが行われました。
 学会会場(富山国際会議場)から撮影。すぐ前にお城が見え、会場までのアクセスもよかったです。
学会会場(富山国際会議場)から撮影。すぐ前にお城が見え、会場までのアクセスもよかったです。
 ランチョンの弁当。なぜカレーがランチョンで出ているのかと不思議に思っていると、薬膳カレーじゃないかということでした(道堯先生説)。さすが富山。残念ながら違いはよくわかりませんでした。
ランチョンの弁当。なぜカレーがランチョンで出ているのかと不思議に思っていると、薬膳カレーじゃないかということでした(道堯先生説)。さすが富山。残念ながら違いはよくわかりませんでした。
研究会では主題で一柳先生が「高齢者の食道静脈瘤治療後に発生する肝不全徴候に関する検討」というタイトルで発表されました。75歳以上の静脈瘤治療では、75歳未満の患者に比べ治療後の食欲低下を来しやすく、遅発性に腹水が発生しやすいことを提言していました。
一般演題で木阪先生が「門脈大循環分流術を施行し肝性脳症と肝予備能が改善した1例」というタイトルで発表しました。肝性脳症を繰り返し発症していた症例で複数のシャントが存在していました。BRTOが施行困難であったためIVRで門脈大循環分流術を施行したという内容でした。経皮経肝的アプローチが可能でBRTO不能例には有効な方法であることを主張しました。
門脈圧亢進症学会総会でも発表しています。
檜垣直幸先生が「3D-CTによる血行動態把握が有用であった十二指腸静脈瘤の2例」で発表しました。ectopic varicesは今年のHepatology Researchに全国調査の成績が掲載されたばかりですが、まれな病態で時に治療に難渋します。このような症例にEIS、BRTO前に3D-CTで血行動態を確実に把握し治療し得たという主旨で発表されました。
宮本安尚先生が「バルーン拡張により穿孔した食道静脈瘤治療後狭窄の1例」で発表されました。静脈瘤治療後通過障害に対しバルーン拡張を施行したものの穿孔をきたし保存的治療により軽快した内容でした。症例は肝癌で左葉切除後であり、このような場合は癒着などにより食道壁本来の弾性を失いやすく穿孔をきたしやすくなる可能性について言及されていました。
中原弘雅先生は「食道・胃静脈瘤が急速に出現した二次性胆汁性肝硬変の1例」で発表しました。多発肝内結石により胆管炎を繰り返し二次性胆汁性肝硬変となり急速に静脈瘤が出現した症例についてプレゼンし、従来のウイルス性肝硬変による静脈瘤の発現との相違を討論されていました。
次回門脈圧亢進症学会は2011年9月15日、16日に福岡で開催されます。
第13回肝不全治療研究会は熊本大学の佐々木先生の当番世話人で開催予定です。