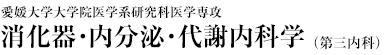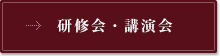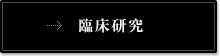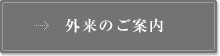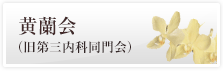急性発症型自己免疫性肝炎 (AIH) の診断基準及び治療指針の策定(愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会承認:愛大医病倫1411008号)
当院では、以下の臨床研究を福島県立医科大学と共同で実施しております。この研究は通常の診療で得られた過去の記録をまとめることによって行います。このような研究は、厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんお一人お一人から直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。
この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、下記の「問い合わせ先」へご照会ください。
【研究機関】愛媛大学医学部附属病院第3内科
【研究責任者】阿部雅則(第3内科准教授)
【研究代表者】大平弘正(福島県立医科大学消化器・リウマチ膠原病内科教授)
【研究の目的】
過去に受診された自己免疫性肝炎患者さんの診療録(カルテ)の情報と肝組織標本を収集し、治療方法や有効性について評価する研究を行うことといたしました。この研究は自己免疫性肝炎における有効な治療方法の検討を目的としたものであり、皆様の今後の診療にも役立つことができると考えています。
【研究の方法】
(対象となる患者さん)平成18年から25年までに当科を受診された方のうち自己免疫性肝炎と診断された患者さん
(利用するカルテ情報)性別、年齢、発症時期、合併症、既往歴、身体所見、血液検査データ、画像検査データ、治療状況 等
(利用する資料)肝生検組織標本(プレパラート)
【個人情報の取り扱い】
収集した情報は名前、住所など患者さんを直接特定できる個人情報を除いて匿名化いたしますので、個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。また、研究結果は学術雑誌や学会等で発表される予定ですが、発表内容に個人を特定できる情報は一切含まれません。この研究の対象となられる方で「ご自身の診療録(カルテ)は除外してほしい」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学医学部附属病院第3内科 阿部雅則
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308
生活習慣病患者を対象とした非アルコール性脂肪性肝疾患の実態調査と予測因子の検討(愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会承認:愛大医病倫1310004号) 当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は通常の診療で得られた記録をまとめることによって行います。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、下記の「問い合わせ先」へご照会ください。
【研究機関】愛媛大学医学部附属病院第3内科
【研究責任者】三宅映己(第3内科特任講師)
【研究の背景と目的】
生活習慣病は、高頻度に脂肪肝を合併することがあります。脂肪肝はアルコールによるものとアルコールに関係ないものに分けられます。アルコールによるものの場合、肝炎、肝硬変、肝臓癌、肝不全に進行することは以前より知られていますが、近年アルコールによらないものの一部にも、肝臓癌や肝不全へ進行する場合があることがわかり、臨床診療の場における重要性は広く認識されています。しかしながら、確定診断には肝生検が必要であり、増加している非アルコール性脂肪肝炎患者の診断において十分な対応ができていません。本研究は生活習慣病患者様の一般外来診療での結果をもとに、肝疾患の診断や予測に寄与する因子を検討し、その有用性を明らかにすることを目的としています。また、継続的にフォローさせて頂き、生活習慣病に関連した合併症(動脈硬化性疾患や癌)の発症に関与する因子についても検討し明らかにします。
【研究の方法】
(対象となる患者さん)愛媛県下の愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学関連施設を受診した患者様のうち
1. 20歳以上の男性女性。
2. 患者本人の自由意思による文書同意が得られた患者様。
参加が難しい方
1.妊婦および妊娠している可能性のある患者様、または授乳中の患者様。
2.肝臓の病気や癌のなどで、全身状態がよくない患者様。
3.その他、研究担当医師が参加して頂くのが難しいと判断した患者様。
(調査項目)入院、もしくは外来診療において通常行っている血液検査、エコー検査、問診です。また、採血の際、同時に血液の一部を保存させていただき(4-6ml程度)、一般外来検査では行われない脂肪性肝疾患や動脈硬化性疾患、癌に関与するに追加の検査を大学の研究費を用いて行います。
これらの結果を用いて、統計学的な解析を行います。
【個人情報の取り扱い】
収集した情報は名前、住所など患者さんを直接特定できる個人情報を除いて匿名化いたしますので、個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。また、研究結果は学術雑誌や学会等で発表される予定ですが、発表内容に個人を特定できる情報は一切含まれません。この研究の対象となられた方で「ご自身の診療録(カルテ)は除外してほしい」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学医学部附属病院第3内科 三宅映己
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308
α‐GI(ミグリトール)のNAFLD,NASHに対する改善効果についての臨床試験 (愛媛大学医学部附属病院臨床研究倫理審査委員会承認:愛大医病倫1406010号) 当院では、以下の臨床研究を実施しております。観察研究を実施することについては、愛媛大学医学部附属病院の臨床研究倫理審査委員会において観察研究実施計画書、参加される方々への説明文書および同意書の内容などについて、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から審査を受け、承認を得ております。
【研究機関】愛媛大学医学部附属病院第3内科
【研究責任者】日浅 陽一(第3内科教授)
【研究の背景と目的】
NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)の患者さまの多くが糖尿病も合併しています。現在、NAFLDの標準的な治療薬は確立されていませんので、各々の合併症に対する治療をすることでNAFLDの改善が認められています。この試験では、2型糖尿病を合併しているNAFLD患者さまの治療薬としてセイブルのNAFLDに対する効果を明らかにすることを目的として検討を行います。
【研究の方法】
(対象となる患者さん)愛媛県下の愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学関連施設を受診した患者様のうち
①HbA1cが6.5から8.0%(NGSP値)の患者さま
①HbA1cが6.5から8.0%(NGSP値)の患者さま
②肝線維化ステージがF2―F3の患者さま
③継続して食事療法・運動療法ができる患者さま
④過去3ヵ月以内に、α-GIのお薬を服薬されていない患者さま
⑤この試験への参加について、同意の能力をもっており、同意文書とその他の説明文書を読む ことができ、理解できる患者さま
⑥年齢20歳以上の患者さま
参加が難しい方
①重篤な慢性肝疾患の患者さま
②重篤な腎疾患を有する患者さま
③重篤な脳血管障害を有する患者さま
④重篤な膵疾患を有する患者さま
⑤癌を有する患者さま
⑥高度な糖尿病性神経障害を有する患者さま
⑦重篤な感染症,重篤な外傷のある患者。手術前後である患者さま
⑧炎症性腸疾患,大腸潰瘍,局所的腸閉塞,腸閉塞素因のある患者さま
⑨消化・吸収異常を伴った重篤な慢性腸疾患患者さま
⑩腸内ガスの発生増加により悪化する疾患・既往のある患者さま
⑪胃切除の既往がある患者さま
⑫妊婦または妊娠している可能性のある女性,妊娠を希望している女性および授乳中の女性の
患者さま
⑬試験開始前の前4ヵ月以内に他の臨床試験に参加した患者さま
⑭試験担当医師が不適当と判断した患者さま
(調査項目)入院、もしくは外来診療において通常行っている血液検査、エコー検査、問診です。また、採血の際、同時に血液の一部を保存させていただき(4-6ml程度)、一般外来検査では行われない脂肪性肝疾患や動脈硬化性疾患、癌に関与するに追加の検査を大学の研究費を用いて行います。
これらの結果を用いて、統計学的な解析を行います。
【個人情報の取り扱い】
収集した情報は名前、住所など患者さんを直接特定できる個人情報を除いて匿名化いたしますので、個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。また、研究結果は学術雑誌や学会等で発表される予定ですが、発表内容に個人を特定できる情報は一切含まれません。この研究の対象となられた方で「ご自身の診療録(カルテ)は除外してほしい」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学医学部附属病院第3内科 三宅映己
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308
原発性胆汁性肝硬変患者のQOL(生活の質)に関する調査研究(愛大医病倫 1507012号)
当院では、以下の臨床研究を多施設と共同で実施しております。この研究は通常の診療で得られた過去の記録をまとめる/保管されている試料を詳しく調べる/及び患者さんへのアンケートによって行います。このような研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんへ研究内容の情報を公開することが必要とされております。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、下記の「問い合わせ先」へご照会ください。
【研究機関】愛媛大学医学部附属病院第3内科
【研究責任者】阿部雅則(第3内科 准教授)
【研究代表者】田中篤(帝京大学医学部内科学講座 教授)
【研究の目的】
原発性胆汁性肝硬変(primary biliary cirrhosis; PBC)は、慢性胆汁うっ滞により徐々に肝の線維化が進行し、無治療の場合には肝硬変及び肝不全へと至る疾患です。近年、治療法の進歩によりPBCの長期予後は大きく改善し、死亡ないし肝移植へと至る症例は大きく減少しました。しかし、PBCは胆汁うっ滞にともなう皮膚掻痒感が初発症状であることが多く、さらに疲労感や口腔乾燥など、数値化することが困難で医療者が認識しにくい症状をしばしば伴い、患者さんがQOL(quality of life; 生活の質)が低下する一因となっています。このため、長期予後だけではなく患者さんのQOLの改善を目的とした治療法の開発が急務であり、そのためにPBC患者さんにおける再現性及び客観性を持ったQOL評価が必要とされています。このような観点から、2007年に帝京大学を中心とした多施設共同研究によりPBC患者さんのQOL調査が行われました。今回の研究では、当院でPBCと診断された患者さんに対しても、同様にQOL調査を行いたいと考えています。
【研究の方法】
研究の参加に同意した患者さんに健康関連QOL評価尺度を用いたアンケート調査用紙を配布、記入を依頼し、記入後各研究参加施設まで送付していただきます。
健康関連QOL評価尺度としては、以下の3種を用います。
①PBC-40
②VAS(皮膚のかゆみの尺度)
③SF-36v2日本語版(健康医療評価研究機構、使用許可済み)
送付された調査用紙は各施設で連結可能匿名化されたのち帝京大学へ送付されます。あわせて、各施設において研究参加患者さんの年齢・性別、職業、臨床情報(血液・画像検査結果、治療内容など)を収集、連結可能匿名化し、帝京大学へ送付します。帝京大学ではこれら調査結果および個人情報を解析し、PBC患者さんの健康関連QOLを評価し、あわせてQOLが社会的状況および疾患の病態によってどのように影響されているかにつき解析します。
【個人情報の取り扱い】
本研究では皆様が受診している病院から個人情報を持ち出すことはありません。
【研究資金および利益相反】
この研究は厚生労働省からの科学研究費補助金を用いて行われます。本研究に関連する企業や団体からの資金援助は受けておらず、利益関係もありません。
【参加拒否の自由】
本研究への参加を拒否することは自由であり、随時参加の撤回をすることが可能です。それにより診療上不利益を受けることもありません。参加拒否を希望される場合は下記までご連絡ください。
さらに詳しい研究の方法をお知りになりたい場合は、「お問い合わせ先」までご連絡ください。他の患者さんの個人情報や知的財産保護等に支障がない範囲でお伝えいたします。
また、この研究の対象となられる方で「ご自身の診療録(カルテ)や保管されている試料(血液や組織など)は除外してほしい」「アンケートに答えたくない」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学医学部附属病院第3内科 阿部雅則
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308
愛媛膵疾患・胆道疾患研究グループ(Ehime Pancreato-cholangiology, EPOCH, Study Group)では、膵癌患者を対象とし、通常の化学療法に成分栄養剤を加え、成分栄養剤の化学療法治療効果に及ぼす影響を評価する臨床研究を実施しております。
今回の臨床研究の対象者は、愛媛大学医学部附属病院または松山赤十字病院へ通院が可能な化学療法が予定されている膵癌患者です。
本臨床研究に関心のある方は、主治医にご相談頂くか下記連絡先までご連絡を下さい。
【問い合わせ先】
791-0295 愛媛県東温市志津川
愛媛大学医学部附属病院第3内科
熊木天児(愛媛大学大学院医学系研究科 地域医療学 准教授)
Tel: 089-960-5308
790-0826 愛媛県松山市文京町1
松山赤十字病院
横田智行(松山赤十字病院 肝胆膵センター 第2肝臓・胆のう・膵臓内科部長)
Tel: 089-924-1111
愛媛大学医学部第三内科では、愛媛大学医学部附属病院の臨床研究倫理審査委員会の承認をえて、広島大学大学院医歯薬保健学研究院・細胞分子生物学研究室と共同で「悪性腫瘍、生活習慣病、ウイルス性肝炎、血液疾患、神経変性症及び精神疾患におけるテロメア不安定性機構の解析」の研究を行っています。(愛大医病倫 1602006号)
学術学会や医学雑誌に結果が発表される場合、個人を特定できる情報が公表されることはありません。また、この研究でえられた結果を個別にご連絡することもありません。
もし、ご自分の血液や組織をこの研究に使用してほしくないとお考えの方は、下記までご連絡ください。
【問い合わせ先】
愛媛大学医学部第三内科 助教 小泉光仁
〒791-0295 愛媛県東温市志津川
電話: 089-960-5308
(平日 9:00~17:00)
当科では、新しい治療法の開発を目指して下記のような治験、臨床研究に取り組んでいます。実施しているのは、いずれも安全性が担保されているものです。また患者様への十分な説明と同意が得られてから実施いたします。このような治療法により治癒したり症状が軽減される事例も多数みられています。ご興味のある患者様、医療関係者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ医局か外来医、病棟医にご相談ください。
臨床研究「自己免疫性肝炎と薬物性肝障害の鑑別診断における血清中自己抗体の有用性に関する検討」
(愛媛大学医学部附属病院臨床倫理委員会承認:愛媛大医病13010016号)
当院では、以下の臨床研究を多施設と共同で実施しております。この研究は患者さんの保存されている血液と通常の診療で得られた過去の記録をまとめることによって行います。このような研究は、厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんお一人お一人から直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。
この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、下記の「問い合わせ先」へご照会ください。
【研究課題名】自己免疫性肝炎と薬物性肝障害の鑑別診断における血清中自己抗体の有用性に関する検討
【研究機関】愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学
【研究責任者・代表者】阿部雅則(消化器・内分泌・代謝内科学 准教授)
【研究の目的】
過去に受診された自己免疫性肝炎および薬物性肝障害の患者さんの保存されている血液および診療録(カルテ)の情報を収集し、治療方法や有効性について評価する研究を行うことといたしました。この研究は自己免疫性肝炎における有効な治療方法の検討を目的としたものであり、皆様の今後の診療にも役立つことができると考えています。
【研究の方法】
(対象となる患者さん)平成12年以降に当科を受診された方のうち自己免疫性肝炎および薬物性肝障害と診断された患者さん
(利用するカルテ情報)性別、年齢、発症時期、合併症、既往歴、身体所見、血液検査データ、画像検査データ、治療状況 等
【個人情報の取り扱い】
収集した情報は名前、住所など患者さんを直接特定できる個人情報を除いて匿名化いたしますので、個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。また、研究結果は学術雑誌や学会等で発表される予定ですが、発表内容に個人を特定できる情報は一切含まれません。
この研究の対象となられる方で「ご自身の情報は除外してほしい」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学 阿部雅則
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308(消化器・内分泌・代謝内科学 医局)
臨床研究「自己免疫性肝炎における抗PCK2抗体の有用性に関する検討」
(愛媛大学医学部附属病院臨床倫理委員会承認:愛媛大医病1310023号)
当院では、以下の臨床研究を多施設と共同で実施しております。この研究は患者さんの保存されている血液と通常の診療で得られた過去の記録をまとめることによって行います。このような研究は、厚生労働省の「臨床研究に関する倫理指針」の規定により、対象となる患者さんお一人お一人から直接同意を得るのではなく、研究内容の情報を公開することが必要とされております。
この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、下記の「問い合わせ先」へご照会ください。
【研究課題名】自己免疫性肝炎における抗PCK2抗体の有用性に関する検討
【研究機関】愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学
【研究責任者・代表者】阿部雅則(消化器・内分泌・代謝内科学 准教授)
【研究の目的】
過去に受診された自己免疫性肝炎および薬物性肝障害の患者さんの保存されている血液および診療録(カルテ)の情報を収集し、治療方法や有効性について評価する研究を行うことといたしました。この研究は自己免疫性肝炎における有効な治療方法の検討を目的としたものであり、皆様の今後の診療にも役立つことができると考えています。
【研究の方法】
(対象となる患者さん)平成12年以降に当科を受診された方のうち自己免疫性肝炎および薬物性肝障害と診断された患者さん
(利用するカルテ情報)性別、年齢、発症時期、合併症、既往歴、身体所見、血液検査データ、画像検査データ、治療状況 等
【個人情報の取り扱い】
収集した情報は名前、住所など患者さんを直接特定できる個人情報を除いて匿名化いたしますので、個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。また、研究結果は学術雑誌や学会等で発表される予定ですが、発表内容に個人を特定できる情報は一切含まれません。
この研究の対象となられる方で「ご自身の情報は除外してほしい」と望まれる方は下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
【問い合わせ先】
愛媛大学大学院医学系研究科消化器・内分泌・代謝内科学 阿部雅則
791-0295 愛媛県東温市志津川
Tel: 089-960-5308(消化器・内分泌・代謝内科学 医局)