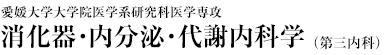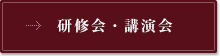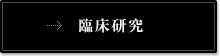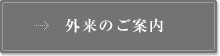抄読会要約まとめのご報告(第四回目)
2011年9月6日 12:19 PM
第三内科で行われた抄読会の内容要約を週1回、同門メールにて現在までお知らせしてまいりました。第三内科ホームページ上でも抄読会内容を確認したいという希望がありましたので、定期的に今後更新してまいります。
第四回目報告をさせていただきます。
[過去抄読会要約のURLリンク]
平成23年 5月
| 抄読者 | 眞柴 寿枝 |
| 論文名 | Virological suppression does not prevent the development of hepatocellular carcinoma in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients with cirrhosis receiving oral antiviral(s) starting with lamivudine monotherapy: results of the nationwide HEPNET. Greece cohort study |
| 著者 | George V Papatheodoridis, Spilios Manolakopoulos, Giota Touloumi, Georgia Vourli,Maria Raptopoulou-Gigi, Irini Vafiadis-Zoumbouli, Themistoklis Vasiliadis,
Kostas Mimidis, Charalambos Gogos, Ioannis Ketikoglou, Emanuel K Manesis, for the HEPNET. Greece Cohort Study Group |
| reference | Gut 2011;60:1109-1116. |
| サマリー | |
| 【目的】 ラミブジン単独での抗ウイルス療法を行われているHBe抗原陰性のB型慢性肝炎患者のHCC発症リスクの評価を行う。
【方法】 12か月以上ラミブジンを投与されているHBe抗原陰性のB型慢性肝炎患者でHCC発生率を解析した。(retorospective-prospective cohort) 患者は818人。うち517人が慢性肝炎、160人が代償期肝硬変、56人が非代償期肝硬変。85人は進行度不明。HCCの発症をend pointとした。 【結果】 平均観察期間4.7年。HCCを発症したのは49名(6.0%)であった。5年間のHCC累積発生率はLCの患者でCHの患者よりも高かった。(11.5% vs 3.2%, p<0.001) 年齢別のHCC発生率は、50歳未満で0.7%、50歳から60歳で6.7%、60歳超で11.7%であった。ウイルス学的な寛解を得られていても、HCCの発症には関係が無かったが、LCよりもCHの患者でHCC発生率が低い傾向にあった。多変量解析では、「年齢、性別、LC」がウイルス学的寛解に関わらずHCC発症の独立因子であった。 【結論】 HBe抗原陰性のB型慢性肝炎患者に対する長期的なラミブジン療法は、HCCのリスクを低下させなかった。とりわけ高齢でLCの患者では、治療効果が得られていてもHCCのスクリーニングは行っていくべきである。ウイルス学的寛解を得られていても、overallでのHCCの発生率の有意な低下はなく、高齢の男性は、HCCの独立危険因子であった。 |
|
| 抄読者 | 竹治 智 |
| 論文名 | Phenotype-dependent production of des-carbixy prothrombin in hepatocellular carcinoma |
| 著者 | Hideto Suzuki et al, Jichi Medical University |
| reference | Journal of Gastroenterology, published online: 09 July 2011 |
| サマリー | |
| 【背景】 肝細胞癌(HCC)のマーカーであるdes-γ-carbixy prothrombin(DCP = PIVKA-Ⅱ)の産生機構は明らかではない。当グループは上皮間葉転換(EMT)等の表現型変化に伴う細胞骨格の再構成が、ビタミンK取り込み障害を介したDCP産生に重要な役割を果たしていることを示している。一方、Transarterial embolization(TAE)後のように低酸素状態が長期間持続する状況でのDCPの産生については知られていない。
【方法】 ヒト肝癌細胞系(HepG2, PLC/PRF/5, AHuh7, SNU-423,HLE,SKHep-1)を用いて、酸素濃度21%と1%、うし胎児血清(FCS) の有り無しの環境下での、上皮系の指標としてE-cadherinの発現量を、間葉系への表現型の変化の指標としてVimentinの発現量等をWestern blot 解析するなど行った。また,同時にHCCの切除標本の免疫組織化学的な検討もなされた。 【結果】 Albumin合成はE-cadherin が発現したHCC細胞でみられ、E-cadherinが発現しないHCC細胞では見られない。また,DCP産生は,albumin合成が行われるE-cadherin発現HCC細胞系でみられる(albumin合成が行われない間葉系性質の強いHCC細胞ではDCP産生はみられない)。一方,E-cadherinの発現したHCC細胞においては、vimentinの発現が強い方がより高いDCP産生がみられる。また、強い低酸素・栄養不良状態のHCC細胞では、albumin合成とDCP産生が、mammalian target of rapamycin (mTOR) pathwayを介して障害された。 【結論】 HCC細胞は、ビタミンK取り込みが障害される表現型変化がマイルドな状態でDCPを産生する。しかし、HCC細胞がより強く間葉系の特性をもつと、mTOR pathwayの低リン酸化を通してDCPを含むタンパク合成能を失い、DCPは減少する。このことから、DCPはHCC細胞の段階的な表現型の変化を反映する唯一の腫瘍マーカーと考え得るかもしれない。 |
|
| 抄読者 | 多田 藤政 |
| 論文名 | Effect of Vitamin E orMetformin for Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children and Adolescents The TONIC Randomized Controlled Trial |
| 著者 | he Nonalcoholic Steatohepatitis Clinical Research Network |
| reference | JAMA Vol.305 , No.16 : 1659-1668,2011/4/27 |
| サマリー | |
| 【背景】 NAFLDはアメリカの小児や青年において最も一般的な慢性肝疾患であり、進行した線維化やNASHがみられる。しかし、治療法は確立していない。
【目的】 NAFLDの小児患者がビタミンE又はメトフォルミンを用いた治療的介入によって改善するかどうかを決定することを目的としてstudyを行った 【研究のデザインと患者背景】 Randomaized,bouble-blind,double-dummy,placebocontrolled clinical trialをデザインし、期間は2005年9月~2010年3月までの4年6カ月で、10か所の大学のclinical research centerで行い。年齢は8歳から17歳までで肝生検でNAFLDと確定診断した173例を対象とした。 【介入】 58例に対して800IU/dayのビタミンE、57例に対して1000mg/dayのメトフォルミン、58例に対してプラセボを96週間(約2年間)投与した。 【Main Outcome Measure】 Primary outcomeは48~96週の間に12週ごとに来院させ基準値の50%又はそれ以下又は40U/L又はそれ以下として定義した持続的なALTの低下とした。NAFLDの組織像の改善やNASHの消退はsecondary outcome measureとした。 【結果】 ALTレベルの持続的な低下はプラセボ群で10/58 17%,ビタミンE群で15/58 26%,メトフォルミン群で9/57 16%とほぼ同様の結果であった。基準から96週までのALTの値の変化の平均はプラセボで35.2U/L、ビタミンE 48.3U/L、メトフォルミン41.7U/Lとこれも優位な差はなかった。96週におけるhepatocellular ballooning scoreの変化の平均はプラセボで0.1、ビタミンEで-0.5(P=0.006)、メトフォルミンで-0.3(P=0.04)であった。NAFLD activity score(NAS)ではプラセボで-0.7、ビタミンEで-1.8(P=0.02)、メトフォルミンで-1.1(P=0.25)であった。小児のNASH症例において、96週で消失した割合はプラセボで28%、ビタミンEで58%(P=0.006)、メトフォルミンで41%(P=0.23)であった。他の組織像においてプラセボと比較しはっきりと改善を示した治療はなかった。 【結論】 小児のNAFLD患者においてビタミンE又はメトフォルミンはATLレベルを持続的に下げるというprimary outcomeを達成することにおいてプラセボと比べどちらも勝っていなかった。 |
|
| 抄読者 | Shiyi Chen |
| 論文名 | Fatty liver index and mortality: The cremona study in the 15th year of follow-up. |
| 著者 | Calori G, Lattuada G, Ragogna F, Garancini MP, Crosignani P, Villa M, Bosi E, Ruotolo G, Piemonti L, Perseghin G. |
| reference | Hepatology. 2011 Jul; 54(1): 145-52. |
| サマリー | |
| A fatty liver, which is a common feature in insulin-resistant states, can lead to chronic liver disease. It has been hypothesized that a fatty liver can also increase the rates of non–hepatic-related morbidity and mortality. In this study, they wanted to determine whether the fatty liver index (FLI), a surrogate marker and a validated algorithm derived from the serum triglyceride level, body mass index, waist circumference, and γ-glutamyltransferase level, was associated with the prognosis in a population study. The 15-year all-cause, hepatic-related, cardiovascular disease (CVD), and cancer mortality rates were obtained through the Regional Health Registry in 2011 for 2074 Caucasian middle-aged individuals in the Cremona study, a population study examining the prevalence of diabetes mellitus in Italy. During the 15-year observation period, 495 deaths were registered: 34 were hepatic-related, 221 were CVD-related, 180 were cancer-related, and 60 were attributed to other causes. FLI was independently associated with the hepatic-related deaths (hazard ratio = 1.04, 95% confidence interval = 1.02-1.05, P < 0.0001). Age, sex, FLI, cigarette smoking, and diabetes were independently associated with all-cause mortality. Age, sex, FLI, systolic blood pressure, and fibrinogen were independently associated with CVD mortality; meanwhile, age, sex, FLI, and smoking were independently associated with cancer mortality. FLI correlated with the homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), a surrogate marker of insulin resistance (Spearman’s ρ = 0.57, P < 0.0001), and when HOMA-IR was included in the multivariate analyses, FLI retained its association with hepatic-related mortality but not with all-cause, CVD, and cancer-related mortality. Conclusion: FLI is independently associated with hepatic-related mortality. It is also associated with all-cause, CVD, and cancer mortality rates, but these associations appear to be tightly interconnected with the risk conferred by the correlated insulin-resistant state. | |
| 抄読者 | 山西 浩文 |
| 論文名 | Pregabalin Reduces Pain in Patients With Chronic Pancreatitis in a Randomized, Controlled Trial |
| 著者 | Olesen SS, Bouwense SA, Wilder-Smith OH, van Goor H, Drewes AM |
| reference | Gastroenterology. 2011 Aug;141(2):536-43. Epub 2011 Apr 14 |
| サマリー | |
| 【背景】・慢性膵炎患者の疼痛は難治性であり、オピオイドを含む鎮痛薬では効果は不十分。
・慢性膵炎患者では中枢神経による疼痛制御の異常がみられ、神経因性疼痛に類似。 ・慢性膵炎患者では膵腺房周囲の神経の肥大、過形成による知覚過敏がみられる。 ・ガバペントイド(pregabalin,ガバペン):神経因性疼痛治療薬。糖尿病性神経障害、ヘルペス後神経疼痛、中枢神経による神経因性疼痛 に使用される。 【目的】 Pregabalinが慢性膵炎患者の疼痛やQOLを改善させるか、また忍容性について検討することを目的とした。 【方法】 ・ランダム二重盲目プラセボコントロール試験 ・64人の慢性膵炎患者をpregabalin投与群34人、プラセボ投与群30人の2群に分けて ①疼痛(投与前1週間と投与後3週間:VAS) ②QOL((EORTC QLQ-C301) ③忍容性(プラセボと比較) を比較検討した。 【結果】 疼痛はpregabalin投与群で有意に改善した。(36% vs 24% ; P > .02) 患者の治療への満足度はpregabalin投与群で有意に高かった。(44% vs 21%; P > .048) QOLは両群間で有意差はみられなかった。 副作用はpregabalin投与群で酩酊感、軽い頭重感は有意差多かった。 重篤な合併症の発生は両群間で有意差はみられなかった。 【結論】 pregabalinは、慢性膵炎の疼痛に対して重篤な副作用なく使用できる有効な補助療法である。 |
|
| 抄読者 | 有光 英治 |
| 論文名 | Stimulation of gastric ulcer healing by heat shock protein 70 |
| 著者 | Tomoaki Ishihara, Shitarou Suemasu, Teita Asano, Ken-ichiro Tanaka, Tohru Mizushima |
| reference | Biochemical Pharmacology 2011 Jun30 |
| サマリー | |
| 【背景・目的】 消化管は様々なストレスに常に曝されており、これらストレスは粘膜障害を誘導し炎症反応を惹起することにより、様々な消化管疾患を引き起こしている。これまでの研究でストレスタンパク質、特にHSP70が細胞内で炎症反応を抑制することが報告されてきた。またテルペン系の化合物(テプレノン:商品名セルベックス)がHSP70を誘導し胃粘膜防御作用を増強することも報告されてきた。本研究ではトランスジェニックマウスを用いたHSP70の胃潰瘍の治癒過程における分子メカニズムを検討するとともに、テプレノンを経口投与した際の胃潰瘍治癒についても検討したので報告する。
【方法】 HSP70を過剰発現したトランスジェニックマウスとWTの胃潰瘍治癒について検討した。潰瘍治癒は酢酸により引き起こされた潰瘍面積を指標に評価した。 【結果】 トランスジェニックマウスではWTと比較して潰瘍の治癒が促進された。トランスジェニックマウスの組織では増殖細胞数の増加と血管新生の亢進が認められた。分子細胞学的にはPGE2、VEGFの産生増加が認められた。テプレノン経口投与によりHSP70の発現が増加し、潰瘍の治癒が促進された。また精製されたレコンビナントのHSP70を経口投与したが潰瘍発生初期(0-3day)に投与しても潰瘍治癒効果はなく潰瘍発生から3-6日後に投与することで潰瘍治癒効果が認められた。 |
|
| 抄読者 | 石原 暢 |
| 論文名 | Efficacy of Selective Transarterial Chemoembolization in Inducing Tumor Necrosis in Small (<5 cm) Hepatocellular Carcinomas |
| 著者 | Golfieri R, Cappelli A, Cucchetti A, Piscaglia F, Carpenzano M, Peri E, Ravaioli M, D’Errico-Grigioni A, Pinna AD, Bolondi L |
| reference | Hepatology. 2011 May;53(5):1580-9. doi: 10.1002/hep.24246. |
| サマリー | |
| 5cm以下の肝細胞癌における腫瘍のネクローシスを引き起こす選択的肝動脈塞栓術の有効性研究の目的は2つあり、1つ目は肝移植の際に病変全体の病理解析をすることによって、腫瘍の壊死において選択的/超選択的肝動脈塞栓術と葉ごとの肝動脈塞栓術の間に違いがあるかを解析することである。
2つ目の目的はTACEで腫瘍の壊死をさせる為の腫瘍の大きさや性質の関係を調査することである。 肝動脈塞栓術を受けたことのある、2003年から2009年の間に肝細胞癌、肝硬変のために肝移植をした患者67人を対象とした。 122の腫瘍のうち53.3%は選択的/超選択的肝動脈塞栓術により治療された。 組織学的な壊死は平均で64.7%であり、完全な腫瘍の壊死は全体の42.6%でみられた。 選択的/超選択的肝動脈塞栓術と葉ごとの肝動脈塞栓術との間には大きな差があり、壊死の平均はそれぞれ、75.1%と52.8%であり、完全な腫瘍の壊死はそれぞれ53.8%と29.8%であった。 腫瘍径と腫瘍の壊死の平均値の間にも関係があり、2cm以下のものでは59.6%、2~3cmのものでは68.4%、3~5cmのものでは76.2%であった。選択的/超選択的肝動脈塞栓術と葉ごとの肝動脈塞栓術を行った際の組織学的な壊死は3~5cmの際にはそれぞれ、91.8%、66.5%であった。 完全な腫瘍壊死の独立予測因子は選択的/超選択的肝動脈塞栓術を単発の腫瘍に行うことであった。 治療の繰り返しも葉ごとの肝動脈塞栓術でより必要となった。(31.6% VS 59.3%) 結論として選択的/超選択的肝動脈塞栓術は葉ごとの肝動脈塞栓術よりも組織学的に完全な腫瘍壊死が起こりやすく、肝動脈塞栓術は3cm以下のものよりも3~5cmのもので最も効果が得られることがわかった。 |
|
| 抄読者 | 山本 安則 |
| 論文名 | Use of Aspirin or Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs Increases Riskfor Diverticulitis and Diverticular Bleeding |
| 著者 | Strate LL, Liu YL, Huang ES, Giovannucci EL, Chan AT |
| reference | Gastroenterology. 2011 May;140(5):1427-33. Epub 2011 Feb 12 |
| サマリー | |
| 【背景及び目的】 非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)(アスピリンを含む)は、憩室の合併症に関係する可能性がある。著者らは、大規模な前向きコホート研究で憩室炎と憩室の出血のリスクに関して、アスピリンとNSAID使用の影響を検討した。
【方法】 米国のHealth Professionals Follow-up Studyに基づき1986年当時40-75歳であった47,210人の男性を調べた。2年ごとにアスピリン、非アスピリン系NSAIDの使用と他の危険因子を評価した。主治医への隔年および補足アンケートを用いて、憩室炎または憩室出血を定義した。 【結果】 追跡評価の22年間の間に、憩室炎939例(約2%)の憩室出血256例(約0.5%)を記録した。危険因子の調整後、定期的に(2回/週)アスピリンを使用した男性では、アスピリンとNSAIDの非使用者と比較して、憩室炎はmultivariable hazard ratio (多変量HR) 1.70(95% CI, 1.05-1.47)、憩室出血は多変量HR 1.70 (95% CI, 1.21-2.39) のリスク上昇がみられた。 中等量(650~1918mg/週)のアスピリンの使用と使用回数の多い例(4~6日/週)は、それぞれ多変量HR 2.32(95%CI、1.34-4.02)と多変量HR 3.13(95%CI、1.82-5.38)であり出血リスクが最も高かった。 非アスピリン系NSAIDの一般的使用者も、非使用者と比較して、憩室炎は、多変量HR 1.72(95%CI、1.40-2.11)、憩室出血は多変量HR 1.74(95%CI、1.15-2.64)のリスク増加を持った。 【結語】 アスピリンまたはNSAIDの定期的な使用は、憩室炎と憩室の出血のリスク増加と関係している。憩室の合併症の危険にさらされた患者は、これらの薬物を使用する潜在的危険と利点を慎重に考慮しなければならない。 |
|
| 抄読者 | 黒田 太良 |
| 論文名 | angiotensin-converting-enzyme inhibitors with angiotensin-receptor blockers in elderly patients a population-based longitudinal analysis. |
| 著者 | McAlister FA, Zhang J, Tonelli M, Klarenbach S, Manns BJ, Hemmelgarn BR; Alberta Kidney Disease Network |
| reference | CMAJ. 2011 Apr 5;183(6):655-62. Epub 2011 Mar 21. |
| サマリー | |
| ACE-ⅠとARBの併用は単剤使用に比べて、糖尿病性腎症患者における腎保護作用の面で有利に働くのではないかという議論があるが、いくつかのRCTでは併用により腎機能悪化のリスクが高くなることが報告されている。一方でRCTでは対象患者が比較的若く、より健康であることや、頻度の低い害について検討するには患者数が少なすぎること、追跡期間が短いことが懸念されている。実臨床における併用療法の実際についてはいまだ不明確であり、本研究では症例対照研究を行いその安全性について検討を行っている。 2002年5月1日から2006年12月31日までにカナダのアルバータ州に登録された診断・生化学・投薬情報を用いてretrospective cohort studyを行った。対象は登録された44301人のうち65歳以上の高齢者で、降圧薬治療開始から数回にわたり血清Cr測定を行っている患者24800人(平均年齢76.1歳、平均Cr 1.07mg/dl)で、ACE-ⅠもしくはARB単剤での治療を行っている患者23376人とACE-Ⅰ・ARB併用療法を行っている患者1424人の比較検討を行った。Primary outcomeは血清Crレベル倍加・透析を必要とするような末期腎不全・死亡の複合アウトカムとした。追跡期間は投薬開始から投薬終了まで、イベント発生まで、患者がアルバータ州を去るまで、もしくは2007年3月31日までとした。
ベースラインの検討では、併用療法群で男性がやや少ない傾向があり、降圧薬以外の循環器系薬剤の投薬{β-blocker,CCB,スタチン,(K保持性以外の)利尿薬}をうけている患者が多い傾向であったが、著者らは併用療法群のうち少なくとも1512人(86.4%)は心不全やタンパク尿を認めなかったと言及している。 結果は、多変量解析を行った後も併用療法群で有意にイベントが発生していた([HR]=2.36;95%CI,1.51-3.71)。ベースとなる血清Crを測定していなかった32312人を対象に、透析を必要とするような末期腎不全・死亡をoutcomeとして解析を行ったが、やはり併用群に有意にイベントが発生しており(adjusted HR=3.27;95%CI,2.01-5.30)、高カリウム血症も併用群に有意にみられた(adjusted HR=2.5;95%CI,1.4-4.3)。 著者らは高齢者におけるACE-ⅠとARBの併用は、単剤による治療と比して腎機能悪化や高カリウム血症のリスクが有意に増加すると結論している。 |
|
| 抄読者 | 三宅 映己 |
| 論文名 | Liraglutide as additional treatment for type 1 diabetes |
| 著者 | Varanasi A, Bellini N, Rawal D, Vora M, Makdissi A, Dhindsa S, Chaudhuri A, Dandona P. |
| reference | European Journal of Endocrinology 2011;165:77-84 Epub 2011 Jun 6. |
| サマリー | |
| 【目的】 インスリン治療中の1型糖尿病患者に対してliraglutideを追加することで、血糖コントロールが改善するかどうか、また、血糖値の変動が改善するかどうかを明らかにすることを目的として検討を行った。
【方法】 血糖値を持続的にモニターリングし、強化療法でよくコントロールされた1型糖尿病患者14人を対象に、一週間のLiraglutideの投与を行った。 【結果】 14人全員が空腹時血糖(130±10から110±8 P<0.01)も、一週間の平均血糖(137.5±20から115±12 P<0.01)も改善した。血糖変動も1週間で優位に改善した(血糖値のmean SDも56±10から26±6 P<0.01へ、変動係数も39.6±10から22.6±7 P<0.01へ改善した)。また、インスリンの使用量もbasalインスリンが24.5±6単位から16.5±6単位へ、bolusインスリンが22.5±4単位から15.5±4単位へ減った。 また、24週間続けてLiraglutideを投与した14人のうち8人は、24週後に、空腹時血糖、HbA1c、血糖値の日内変動、インスリン投与量、体重の低下がみられた。 血糖値改善作用のメカニズムとしては、グルカゴンの抑制と食物の胃内からの排泄遅延による食後の血糖値の改善が考えられた。 【結論】 Liraglutide治療は1型糖尿病患者の血糖コントロールの新しい治療法となりえる。 |
|