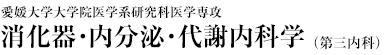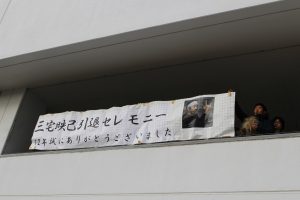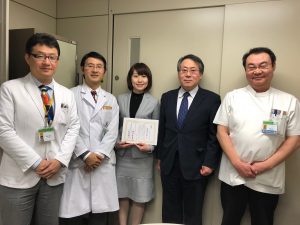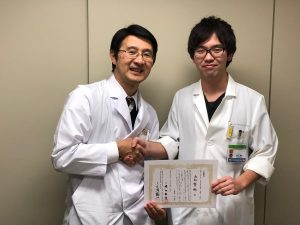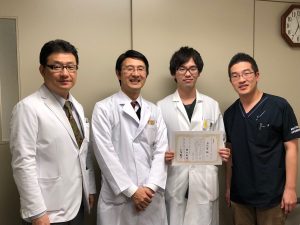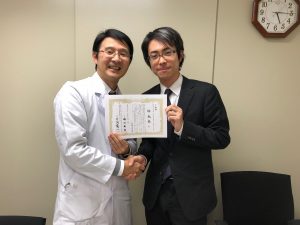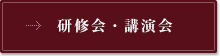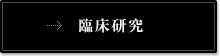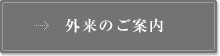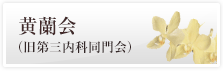〇第13回愛媛免疫疾患研究会
日時:2月3日(土)17:00~19:00
リジェール松山
特別講演Ⅰ
新潟大学 保健管理センター 准教授 黒田 毅先生
特別講演Ⅱ
済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科 部長 乾 あやの先生
〇潰瘍性大腸炎適応追加講演会in愛媛
日時:2月7日(水)19:30~21:00
大和屋本店
特別講演Ⅰ
東邦大学医療センター佐倉病院 消化器内科 教授 鈴木 康夫先生
特別講演Ⅱ
横浜市立大学医学部 がん総合医科学 教授 窪田 賢輔先生
〇第5回愛媛肝胆膵腫瘍研究会
日時:2月10日(土)17:00~19:20
松山全日空ホテル南館4階 「エメラルドルーム」
特別講演
横浜市立大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 准教授 松山 隆生先生
〇IBD Expert Meeting in 松山
日時:2月16日(金)19:30~20:30
いよてつ会館3階 「ロビンルーム」
特別講演
愛媛県立中央病院 消化器内科 部長 森 健一郎先生
〇消化器疾患セミナー
日時:2月21日(水)19:00~
松山全日空ホテル南館4階 「エメラルドルーム」
特別講演Ⅰ
京都府立医科大学大学院医学系研究科 消化器内科学 講師 阪上 順一先生
特別講演Ⅱ
日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野 主任教授 森山 光彦先生
〇膵・消化管神経内分泌腫瘍セミナーIN愛媛
日時:2月27日(火)19:15~20:35
リジェール松山7階 「シルバーホール」
特別講演
京都大学大学院医学研究科 腫瘍薬物治療学講座 准教授 松本 重巳先生
〇第4回肝臓と糖尿病・代謝研究会in愛媛
日時:2月28日(水)19:00~
松山全日空ホテル南館4階 「エメラルドルーム」
特別講演
順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学 教授 綿田 裕孝先生
〇第44回愛媛内分泌代謝疾患懇話会
日時:3月8日(水)19:00~21:00
道後山の手ホテル2階 「ビクトリアホール」
特別講演Ⅰ
首都大学東京 人間健康科学研究科 ヘルスプロモーションサイエンス学域
准教授 眞鍋 康子先生
特別講演Ⅱ
愛媛大学 産婦人科学 教授 杉山 隆先生
〇地域医療連携カンファレンス
日時:3月14日(水)19:00~20:10
愛媛大学医学部 第1ゼミナール室
特別講演Ⅰ
愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター 准教授 廣岡 昌史先生
特別講演Ⅱ
愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学 教授 日浅 陽一先生
〇第148回愛媛糖尿病同好会
日時:3月23日(金)18:50~
松山市総合コミュニティセンター3階 大会議室
特別講演
群馬大学生体調節研究所 教授
生活習慣病解析センター長 北村 忠弘先生
〇第69回愛媛肝胆膵研究会
日時:3月24日(土)16:00~18:30
松山市民病院 永頼会館
特別講演Ⅰ
大阪医科大学 第二内科 講師(准) 小倉 健先生
特別講演Ⅱ
兵庫医科大学 肝・胆・膵内科 主任教授 西口 修平先生
〇Liver Sciences Forum in 愛媛
日時:3月28日(水)19:00~20:30
松山全日空ホテル4階 「ダイヤモンドルーム」
特別講演
国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター センター長 考藤 達哉先生