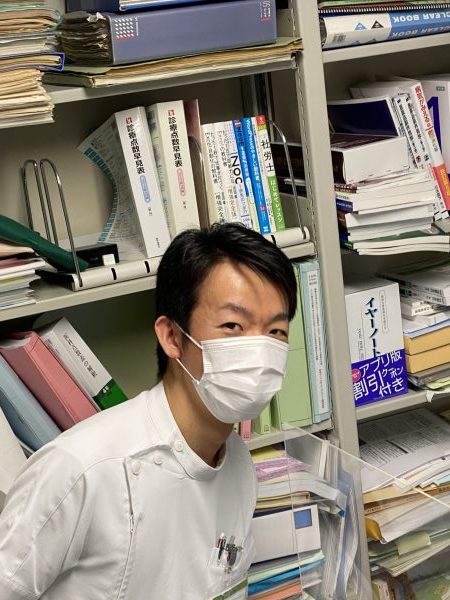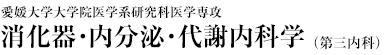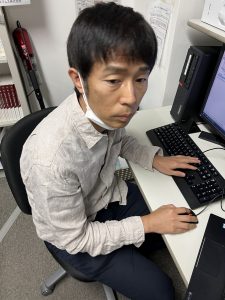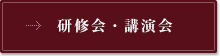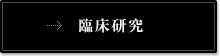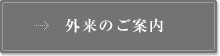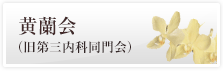教室の盛田真先生の症例報告「肝硬変による難治性乳び腹水に対してプロプラノロールが奏功した1例」が雑誌「肝臓」にアクセプトされました
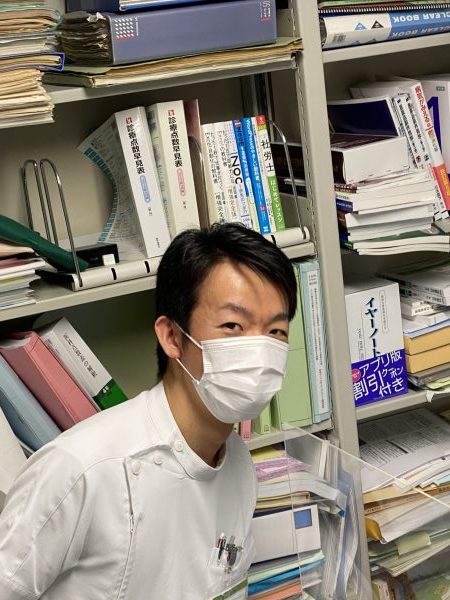
肝臓グループのホープ:盛田先生
以下、盛田先生のコメントです。
肝硬変では頻度は少ないですが乳び腹水を発症することがあり、発症機序に門脈圧亢進が関係していると考えられています。一般的に脂肪制限食、塩分制限、利尿薬で治療を開始し、改善が得られなければ絶食、中心静脈栄養、オクトレオチド投与を検討します。リンパ管損傷が疑われる場合はリンパ管造影も検討します。本症例は上記の治療で腹水の減少がみられなかったため、門脈圧亢進に対する治療としてプロプラノロールを開始したところ、腹水の著明な減少が得られました。肝硬変による乳び腹水に対してプロプラノロールは検討に値する治療法と考えられ、報告させていただきました。
論文作成にあたり多大なるお力添えをいただきました松山赤十字病院の越智先生、肝胆膵内科の先生方に厚く御礼申し上げます。今後も学会発表、論文にできる症例を探すつもりで診療にあたりたいと思います。
矢野怜先生の症例報告がInternal Medicineにアクセプトになりました。
以下、矢野先生からのコメントです。
タイトルは”A case of metastasis from renal cell carcinoma to ectopic pancreas diagnosed after resection”です。腎細胞癌術後10年経過して、膵臓に再発を来した症例です。治療として膵頭十二指腸切除を行うと、切除した十二指腸の中の異所性膵にも腎細胞癌の転移を認めました。
転移性膵腫瘍の原発として腎細胞癌は稀ではありませんが、異所性膵に転移した腎細胞癌の報告は無く、本症例が初めての報告になると思います。
本症例は腎細胞癌の一部には膵組織に転移・発育しやすいものがあるという、癌における「Seed and Soil theory」という考えを支持するのではないかと思っています。
症例報告にあたりご指導いただきました松山赤十字病院の横田先生、肝胆膵センターのスタッフの皆様に深く感謝を申し上げます。
矢野怜 拝

〇HCC Basic Research Web conference
日時:8月10日(水) 19:00~20:30
完全Web形式による実施となります。
ご視聴にあたっては、事前参加登録をお願いいたします。
講演1
愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学
助教 渡辺 崇夫 先生
講演2
国際医療福祉大学 医学部長
医学研究科 免疫学 教授
河上 裕 先生
〇LENVIMA-HCC Web Seminar in 愛媛
日時:8月17日(水) 19:30~20:30
完全Web形式による実施となります。
ご視聴にあたっては、事前参加登録をお願いいたします。
基調講演
愛媛県立中央病院 消化器内科
主任部長 平岡 淳 先生
特別講演
虎の門病院 肝臓内科
医長 保坂 哲也 先生
★HCC Basic Research Web conference 案内状
220817_LENVIMA-HCC Web Seminar in 愛媛(最終版)
〇愛媛県の胆膵疾患を考える会
日時:7月22日(金) 19:00~
会場:ANAクラウンプラザホテル松山 南館4階「エメラルド」
会場とZOOM配信によるハイブリッド形式となります。
ご視聴にあたっては、講演会当日までに参加登録をお願いいたします。
基調講演
愛媛県立中央病院 消化器内科
部長 黒田 太良 先生
特別講演
大阪医科歯科大学 第二内科
准教授 小倉 健 先生
〇愛媛下垂体疾患研究会(大学院特別講義)
日時:7月22日(金) 18:20~20:00
場所:愛媛大学医学部 臨床講義棟 2F 臨床第一講義室
一般演題
<1>愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
國廣 丞史 先生
<2>愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学
越智 拓哉 先生
<3>愛媛大学大学院医学系研究科 小児科学 講師
濱田 淳平 先生
特別講演
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科
脳神経外科学 藤尾 信吾 先生
〇第2回 治療と仕事の両立支援セミナー
日時:7月26日(火) 19:00~20:30
会場:ホテルマイステイズ松山 2階「フェスタ」
ZOOM配信による完全Web形式となります。
事前に参加登録をお願いいたします。
基調講演
愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター
愛媛県難病医療コーディネーター
日本難病看護学会認定 難病看護師 西岡 理可 先生
愛媛大学大学院医学系研究科 難病・高齢医療学講座
教授 越智 博文 先生
特別講演
産業医科大学 産業生態科学研究所 産業精神保健学研究室
教授 江口 尚 先生
【確定】愛媛県の胆膵疾患を考える会
[最終完成版]2022.07.22愛媛下垂体疾患研究会 ご案内
第2回治療と仕事の両立支援セミナー
今週末(2022年6月18日、19日)に第128回日本消化器内視鏡学会四国支部例会が松山市総合コミュニティセンターで開催されます。
皆さんのご参加をお待ちしております。

愛媛大学大学院医学系研究科 地域消化器免疫医療講座の竹下英次先生(会長)と丹下和洋先生(事務局長)
愛媛県立中央病院の平岡淳先生が日本肝臓学会英文誌”Hepatology Research” 2022年度High Citation awardを受賞されました。

以下、平岡先生がコメントを送ってくれました。
日本肝臓学会英文誌”Hepatology Research” 2022年度High Citation awardを受賞して
愛媛県立中央病院 消化器内科 主任部長 平岡淳
このたび栄誉ある”Hepatology Research” 2022年度High Citation awardを受賞しました。
”Hepatology Research”は日本肝臓学会の英文誌で論文採択難度の高いジャーナル(Impact factor 4.2)の1つです。
“Therapeutic potential of lenvatinib for unresectable hepatocellular carcinoma in clinical practice: Multicenter analysis.
Hiraoka A, Kumada T, Kariyama K, Takaguchi K, Itobayashi E, Shimada N, Tajiri K, Tsuji K, Ishikawa T, Ochi H, Hirooka M, Tsutsui A, Shibata H, Tada T, Toyoda H, Nouso K, Joko K, Hiasa Y, Michitaka K; Real-life Practice Experts for HCC (RELPEC) Study Group and the HCC 48 Group (hepatocellular carcinoma experts from 48 clinics in Japan). Hepatol Res. 2019;49(1):111-117. “
上記の受賞論文は愛媛県立中央病院だけではなく、愛媛大学をはじめとする全国の多施設共同研究複合組織のRELPEC/HCC48を母体として集積したデータを解析して論文化したものの1つです。
切除不能肝癌に対する一次治療薬として分子標的治療薬レンバチニブが保険収載されたわずか半年後に執筆投稿publishとなった肝癌に対するレンバチニブ初の実臨床論文です。肝予備能が良好な症例に対して実臨床においても臨床試験(治験)結果と同様に良好な治療効果が得られること、一次治療としてだけではなく二次治療以降の治療として使用しても同様な治療効果得られることが示されました。
今回頂いた賞を励みにこれからも臨床の現場に還元できる研究を診療とともに続けて行きたいと思います。
多施設共同研究複合組織に参加されている皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます、本当にありがとうございました。
2022年5月20日から22日の3日間にわたり、名古屋国際会議場で日本超音波医学会第95回学術集会が開催されました。第95回学術集会ファイヤーサイドトーク内で授賞式が開催され、日本超音波医学会(英文誌)「Journal of Medical Ultrasonics」Vol. 48, No.2に掲載された論文の「Noninvasive ultrasound technique for assessment of liver fibrosis and cardiac function in Fontan‑associated liver disease: diagnosis based on elastography and hepatic vein waveform type」で小泉洋平先生が第17回伊東賞(論文賞)を授賞されました。また、丹下正章先生が日本超音波医学会第95回学術集会新人賞を授賞されました。
以下小泉先生より
2016年の日本超音波医学会第11回伊東賞(論文賞)に続いて、今回、このような栄誉ある賞を頂くことができ、とても光栄に思っております。これもご指導いただきました日浅先生、廣岡先生あってのことと深謝しております。今後も精進していきたいと思っておりますので,今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

伊東賞、菊池賞受賞の先生方

新人賞の先生方

現超音波医学会理事長の椎名 毅先生、次期超音波医学会理事長に選出された飯島 尋子先生と
〇ARNI Web Symposium ~高血圧と糖尿病を考える~
日時:6月13日(月) 19:00~20:00
Microsoft TeamsによるWeb形式となります。
ご視聴にあたっては、事前に参加登録をお願いいたします。
特別講演
岡山大学学術研究院医歯薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学
准教授 江口 潤 先生
〇愛媛県下垂体疾患WEBセミナー2022
日時:6月17日(金) 19:00~20:30
会場:ANAクラウンプラザホテル松山 本館3階「ローズルーム」
現地開催と同時Webライブ配信による実施となります。
ご視聴にあたっては、事前に参加登録をお願いいたします。
一般講演
愛媛県立中央病院 糖尿病・内分泌内科
部長 宮内 省蔵 先生
特別講演
奈良県立医科大学 糖尿病・内分泌内科学講座
教授 髙橋 裕 先生
〇愛媛県SURIセミナー~ユリス錠発売2周年記念講演会~
日時:6月20日(月) 19:00~20:00
Zoom配信による実施となります。
ご視聴にあたっては、事前に参加登録をお願いいたします。
講演
香川大学医学部 薬理学
教授 西山 成 先生
〇愛媛県UCフォーラム
日時:6月24日(金) 19:00~20:30
会場:ろうきんビル 5階「会議室」
会場開催とネット回線を介したハイブリッド形式の講演会となります。
ご視聴にあたっては、事前に参加登録をお願いいたします。
※会場視聴も事前予約必要:座席に限りがございます。
講演①
愛媛県立中央病院 消化器内科
医長 IBDセンター長 北畑 翔吾 先生
講演②
京都府立医科大学 消化器内科
准教授 髙木 智久 先生
〇第2回愛媛肝疾患連携セミナー
日時:6月29日(水) 19:00~20:30
会場およびオンラインでのハイブリッド開催となります。
ご視聴にあたっては、事前に参加登録をお願いいたします。
講演 19:00~19:25
愛媛大学医学部附属病院 肝疾患診療相談センター
副センター長 今井 祐輔 先生
講演 19:25~19:50
済生会西条病院 臨床検査科 吉田 香里 先生
済生会西条病院 看護部 小橋 範子 先生
講演 19:50~20:15
松山市民病院 消化器内科
部長 木阪 吉保 先生
2022年6月13日ARNI Web symposium 高血圧と糖尿病を考える
【案内状】愛媛県下垂体疾患WEBセミナー2022_参加登録マニュアル
確定20220620愛媛県SURIセミナー
0624愛媛県UCフォーラム
【案内状】 第2回愛媛肝疾患連携セミナー2022
山本安則先生と総合健康センターの古川慎哉先生がまとめた「笑い」と機能性ディスペプシア との関連性について研究結果がInternational Journal of Environmental Research and Public Health (IF 3.390)にアクセプトされました。
以下古川先生からのコメントです。
「笑い」は様々な病気の予防に役立つとされており、NK細胞などの免疫能の改善や食後高血糖の予防に加えて、動脈硬化疾患も予防的に働くことが報告されています。笑いと消化器疾患との関連については、過去2法報告があり、過敏性腸症候群では笑いヨガでは症状が緩和することや機能性胃腸障害に効果があったことが報告されていましたが、機能性ディスペプシアにおいてはエビデンスがありませんでした。また、「笑い」の場面ごとの健康へ与える効果は過去の先行研究でも解析されていませんでした。
愛媛大学の学生検診データを活用して、自己申告の「笑い」、「笑う場面」と機能性ディスペプシアとの関連性について解析を行いました。
自己申告の全体「笑い」の頻度とFDとの関連性はありませんでした。一方で、笑いの種類と機能性ディスペプシアとの関連性については興味深い解析結果が明らかになりました。
「ほぼ毎日友人や家族など他人と一緒に笑う」では有意に機能性ディスペプシアの有病率が低く、その頻度と負の関連性がありました(調整後オッズ比0.47 [95% 信頼区間: 0.28–0.81], p for trend = 0.003)。
一方で、「テレビやビデオを見ながら笑う」や「漫画などで笑う」ではむしろ機能性ディスペプシアが有意に多い結果でした(テレビやビデオでの笑い(週に1から5回)調整後オッズ比1.74 [95% 信頼区間: 1.16–2.60]、漫画での笑い(週に1から5回)調整後オッズ比1.78[95% 信頼区間: 1.08–2.81])
なぜ「ほぼ毎日友人や家族など他人と一緒に笑う」と機能性ディスペプシアが少ないかについてはいくつかの機序が考えられます。
1)一般的に鬱症状は機能性ディスペプシアとのリスクとされており、笑いが鬱症状の緩和を介して機能性ディスペプシアを予防した可能性
2)他人との一緒に笑うことでオピオイド類が分泌され、痛みの閾値が変化した可能性
3)笑うことは健康的な証である可能性
4)とくに他人と一緒に笑えることは社会的な絆が強いことを意味しており、社会的絆が強いと、コルチゾールをさげ、オキシトシンの濃度を高めまった可能性(ヒトの先行研究)
5)その結果としてコルチゾールは内臓過剰反応を抑制し、オキシトシンは胃の排出能を高めた可能性
一方で、話のオチを聞くと、交感神経を亢進させることが先行研究で示されており、テレビや漫画などでの笑いは機能性ディスペプシアのリスクを高めた可能性が考えられます。(実は、我々のことを考えて?、三宅映己先生がオチない話もされているかもしれません。)
本研究では「家族や友人と一緒に笑うこと」が機能性ディスペプシアに予防的に働く可能性、「笑い」には種類があり、健康へ与える効果が異なる可能性が示唆されました。今後、笑いの介入研究等で因果関係を解明する必要があるかもしれません。
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は、適切な治療が行われなかった場合、肝硬変や肝不全に進行したり、肝臓癌を合併するだけでなく、心血管疾患発症の危険因子となり、進行したNASHは予後不良の疾患です。一方で糖尿病は、神経障害、網膜症、腎症の三大合併症や心血管疾患の危険因子となるだけでなく、NASHを進展させる最も重要な因子の一つと考えられています。そのため、進行する危険性の高いNASHが多く存在する糖尿病外来での適切なNASHの診断と治療介入が重要です。しかしながら、NASHの標準的治療法として確立されたものはありません。
本研究は、未だ確立されていない2型糖尿病合併NASHに対する有効な治療法の選択肢の一つになるうる可能性があるGLP-1受容体作動薬、SGLT2阻害薬の併用療法の有効性を検証し新たなエビデンスを確立するための探索的非盲検無作為化並行群間比較試験です。
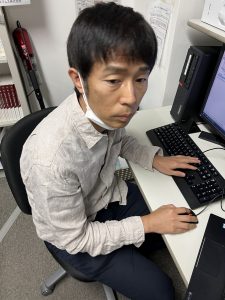
「2型糖尿病合併NASH患者を対象としたセマグルチド注へのルセオグリフロジン上乗せNASH改善効果に関する探索的研究(非盲検無作為化並行群間比較試験)」
本研究に参加して頂ける患者様を募集しております。
是非、ご協力頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。
プロトコル論文です。お時間のある時にご覧ください。
Additional Effect of Luseogliflozin on Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis Complicated by Type 2 Diabetes Mellitus: An Open-Label, Randomized, Parallel-Group Study」Diabetes Ther. 2022 Mar 21. doi: 10.1007/s13300-022-01239-7.